|
◆「ビリヤードニイッテ、ツタヤニイク」
自動車保険の更新手続に、たいしも連れてトヨタカローラに行きました。
たいしはいつものように2階へまっすぐ上がり、すぐテレビゲームを始めました。
手続の方はそれほど時間がかからなかったので、これはやめるのにもたつくかなぁーと思いきや、「たいし、帰るよ」と声をかけると、意外にもすんなりやめてテレビのスイッチも自分で切ってくれました。
トムとジェリーのDVDがつけっぱなしになっていて(これもたいしがつけたんだと思います)、これを私がとめようとしたら、ミッキーのDVDを取り出したりして、これでちょっとだけもたつきました。
「次はどこへ行く?」ときくと、「ツタヤ」。「ビリヤードは今日は行かない?」「ビリヤードニイッテ、ツタヤニイク」。
そうかい、欲張りだねー、とその時は思ったのですが、2カ所の予定を立てられるようになったんだ、と後で気がつきました。
◆がまんできるよ
翌日も、トヨタカローラに携帯電話の申込みに行きました。なぜか携帯の子会社が中にあるので、知ってる営業マンにお願いしました。待っている間、たいしを遊ばせておけるな、と思って連れていきました。
店に着くと、たいしは2階へまっしぐら。ところが、携帯の登録の手続きはその店ではできないので、登録するのに日にちがかかること、別の営業所ならすぐできるからそっちへ行ってほしいということになっちゃった。おーっと、それは予定外。
「ミュー、たいし連れてきて。別の店に行くから」
ミューが2階へたいしを迎えに行くと、長靴もジャンバーも脱いで遊ぶ態勢に入っていたたいしでしたが、靴をはき直して降りてきました。「さあゲームやるぞ!」という一番ごねやすいタイミングだったと思います。 えらいぞ、たいし! 連れてきたミューもえらい!
ここでたいしがはまるようであれば、多少日にちがかかってもこの店で手続きしようかとも思いましたが、なんとゲームやるのを中断できました。
さらに、たいしがジャンバーを忘れたので、もう一度2階に取りに行かせましたが、ちゃんと持って降りてきました。
別の営業所には、テレビゲームはないようでしたが、本屋さんが入っていて、たいしはうろうろしながら、わりとおとなしく本やテレビを見ていました。
自分がやりたいことへのこだわりが少なくなったのか、がまんできるようになったのか、その日はパニクることもなく、家に帰ってきたあとも、ビデオをみたりパソコンをいじったりしながらおだやかに過ごしました。
◆ママがいなくてもだいじょうぶ
三学期はずっとママが教室に入ってましたが、4年生に向けて2時間だけ教室を抜けました。たいしは、いつものようにしており、パニクることもなくだいじょうぶだったということでした。
といっても、1時間目はビデオ(以前はドラえもんでさえいやがって教室を出ていたんですが、ちゃんと席にいたそうです)で、2時間目はパソコンでしたが。パソコンの時間は、他の子が先生の指示で操作している間、たいしは、おとなしくインターネットでドラえもんを見てました。
|
〔いすとりゲーム〕

♪チャーンチャカチャカ・・・

「アッ!」 曲が止まった!
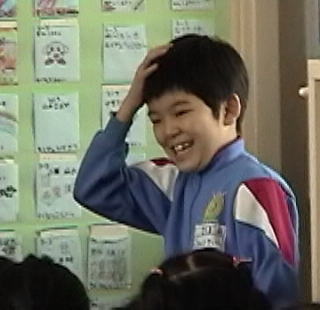
イシシシ・・・
|
◆「アキコチャン、ヤッツケロ」
最近、たいしは、「オニゴッコスル」と友だちを誘うようになりました。たいしが誰かに誘いかけると、数人が集まってきます。そして、おにごっこをすると「たいしくん、走るの速くなった。なかなかつかまえられなくなっちゃった」と子どもたちの感想。たぶん、友だちと追いかけたり追いかけられたりすることを楽しいと感じることができるようになって、目的意識が出てきたんでしょう。ものすごい速さで走ってきてタッチすることがあるという話です。
さて、その日、昼休みにおにごっこをしていると、ひろきくんが、ねずみの真似をし始めました。床にはいつくばってチュウチュウ。すると、たいしがそのねずみを指さしながらあきこちゃんの手首をひっぱって自分の前に立たせ、「アキコチャン、ヤッツケロ」と言ったそうです。
友だちへの働きかけが次々と発展していきます。
◆“勇気”って
国語の時間に「モチモチの木」の授業がありました。夜はこわくておしっこにも行けないほど臆病者なのに、腹痛で苦しみだしたおじいちゃんのために、夜中に裸足で外へ駆け出し、お医者さまを呼びに行った子どもの話。
そこで、先生は“勇気”の話をしました。その中で「“勇気”ってなんだ? ・・・このまえ、みんなはスキーのリレーで、たいしくんが遅いから負けるって思っても、リレーからはずしたり、たいしくんをひっぱって早くすべらせるとかずるしたりしないで、精いっぱいたいしくんを応援して、自分でも精いっぱいがんばったよな。それも勇気なんだ」という話をしました。
うーむ。 親が子どもの障害を受容するのは“勇気”かも知れない。普通学級の先生が障害のある子を担任するのも“勇気”かも知れない。でも、子どもたちはどうなんだろう? はじめは“変な子”、“ムカつくやつ”と思った子もいたかも知れないけど、もう、たいしがいて当たり前になっちゃったんじゃないだろうか。 たいしも“クラスの仲間”というのを自然に受け止められる子にとっては“当たり前”のことで、それを“勇気”と言われてもピンとこないような気がしないでもない。 もっともクラス全員がそうかと言えばそうも言い切れません。
現実をありのままに受け入れるということは、確かに“勇気”なんだと思います。障害児者を受け入れるのに“勇気”の必要がない世の中になればいいと思います。
|
|